昨年から公的機関の仕事で発注元(親事業者)と発注先(下請け事業者)の事業者を訪問させて頂く機会が多くなりました。
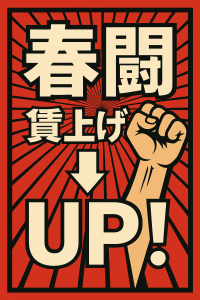
この前訪問させて頂いた発注元の事業者では、仕入先からの値上げ申請の対応で忙しいと言われてました。又、仕入先からの値上げの話しはしっかり聞く様にしてるという会社も多く見られる様になり、値上げ申請に対する発注元の姿勢も少しずつ変わりつつあります。
一方、発注先(下請け事業者)の経営支援をしていると、なかなか価格交渉が進まない現実をまの当りにします。先般、値上げ申請の支援をした事業者からお電話を頂いたのは、「客先に値上げ申請をしたが、冷たい回答しかなくどうしたら良いか」とご相談を頂きました。又、ある中小企業の社長の値上げ申請のご相談では、どう見ても下請法違反ととれる様な取引で、中小企業診断士、一個人の支援では何とも出来ない歯がゆい案件でした。
さて、巷のニュースでは春闘の時期になり、大企業では大幅なベースアップで妥結しつつあり、中小企業の賃上げ6%目標と言う大きな見出しも見る様になりました。しかしながら、現実は厳しく中小企業の経営者は、それどころではないのが現状です。中小企業の半数以上が赤字経営と言われている中で、どうやったら賃上げが出来るんだと言う社長のボヤキが聞こえて来そうです。
これまで、中小企業庁、公正取引委員会では、下請法違反を監視するために全国に「下請けGメン」、相談窓口としての「かけ込み寺」を設置、アンケートの実施、親事業者の監査と強化をして来ましたが、下請法違反が後を絶たなく、価格転嫁もなかなか進んで来ませんでした。そこで、政府は下請法を強化し、価格転嫁を強力に進め中小企業の賃上げを支援しようと下請法の改正を予定しています。
下請法は、下請代金支払遅延等防止法と呼び、下請取引の公正化と下請事業者の利益保護を目的とし1956年(翌年施行)6月1日に日本の中小企業を保護するために制定された法律で、大企業が中小企業に対して「代金の未払い」「支払い遅延」「不当な減額」「返品の強要」など不利な取引条件を強いることを防ぐために設けられました。
下請法は制定以来、何度か改正されていますが、今通常国会に提出され50年ぶりとなる大幅な改正が行われます。
改定の主なポイントは、資本金の操作による下請法逃れを防止する「資本金基準の見直し」、下請事業者との十分な協議を欠いた不当な価格設定や、原材料費の高騰を反映しない価格決定を防止するための「買いたたき規制の強化」、手形支払から現金支払への移行や、支払期日を現行の120日以内から60日以内に短縮する「支払い条件の直し」、従来の製造・修理委託、情報成果物作成委託、役務提供委託に加え、物流分野への「適用業務の拡大」、主従関係を連想させる「下請け事業者」を、取引関係の対等性、事業者間の協力関係を適切に表現する「中小受託事業者」という「下請け用語の変更」等です。
今回の下請法改正により、下請け事業者の保護が強化され、取引の公正性が一層高まることが期待されます。賃上げの必要性が叫ばれる中で、中小企業が適正な価格で取引を行い、健全な経営を維持できる環境を整えることが重要だと考えます。今後も政府の取り組みや発注元企業の対応に注目しながら、中小企業の支援に尽力していきたいと思います。
中小企業診断士 清水 英範

